この時期、もうすぐ入学、進級というお子さんをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。新しい学校やクラスに期待が膨らむ一方で、教科書など新しいモノもドカンと家の中に入ってきます。親としてはどこにどう片づけるべきか、また古いモノはどうしたら良いかと悩ましいところでしょう。
既に大学生になった私の娘は自分で勝手にチャッチャと身の回りを整頓してくれています。息子も高校生なので親としては手慣れたものです。しかし、子供たちが小学生の頃はそれなりに試行錯誤していました。
その時の様子がリアルで分かりやすいと感じたので、再掲したいと思います。なお、記事の後半では、よそのお宅の事例やアンケート結果も掲載しています。参考にしてみてください。
※この記事は2016年4月11日公開の記事をリライトしたものです(2024年3月26日更新)
古い教科書は何のために保管しておく?
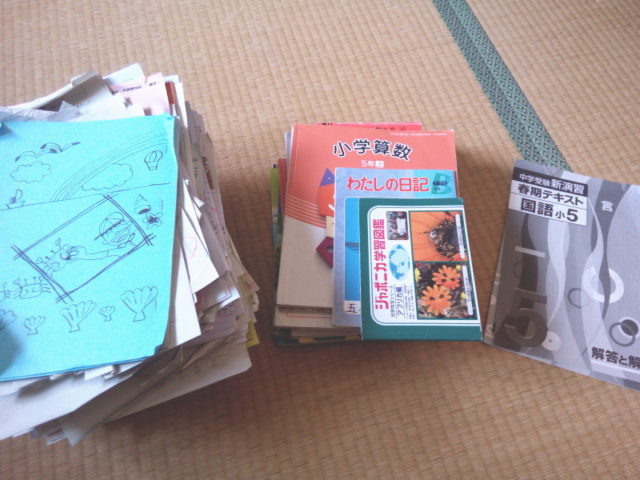
4月からの新学年。小学校6年生になった娘は新しい教科書を持ち帰ると、代わりに5年生の教科書やノート、プリントなどを本棚から取り出し、「これはもう要らない」と言って積み上げました。それを見て妻は「もう置く場所がない。どこに置いたら良い?」と私に聞いてきました。
そこで私は妻に聞きました。

何のために教科書を取っておくの?
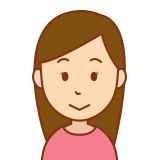
うーん…。
返答に困る妻。

○○○(小学校3年生になった息子)が教科書をなくす可能性があるから、そのためじゃないの?
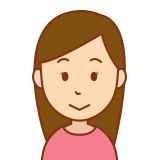
なるほど、そうだよね。
ということで、教科書だけを残して残りは処分することにしました。つまり、ノートやプリントはすべて処分。ただし、日記だけは思い出の品として残すことにしました。
過去の経験から、使いかけのノートは処分
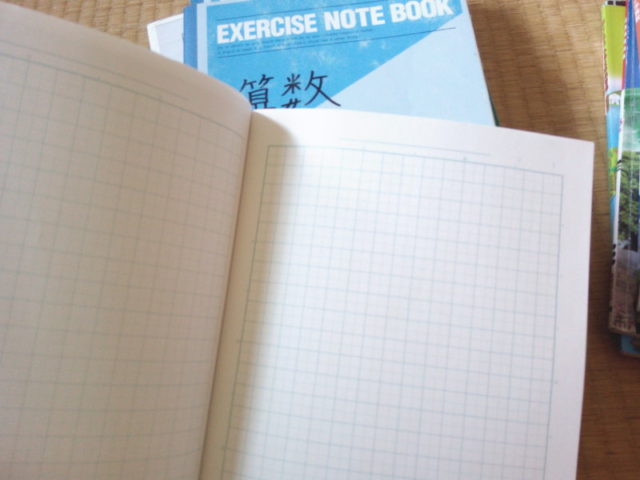
その過程で、使いかけのノートも数冊出てきました。最初の数ページだけ使って残りは真新しいものも2~3冊ありました。
これらは使おうと思えば使えます。使う可能性があるわけです。しかし、私の経験から言うと、それらを取っておいたところで使うことがないのです。メモ用紙なら他にたくさんあります。ですから、使いかけのノートは不確定要素に賭けず、過去の経験に基づいて処分することにしました。
古い教科書やノートがいっぱい出てきた

結果、娘が5年生で使った教科書やノートなどは、教科書だけを残すことで1/5程度のボリュームになりました。めでたしめでたし…と思ったら、妻がクローゼットの中をゴソゴソと掘り起こしてダンボール箱や紙袋が出てきました。
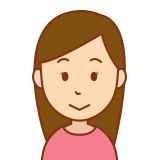
じゃあこれも要らないモノは捨てたら良いのかな?
見てみると、小学校1年生から4年生まで娘が使った教科書やノート、プリントの山。息子が1年生で使った教科書なども出てきました。

教科書を取っておく目的は、○○○(息子)が教科書をなくしたときのため。それなら3年生以降の分だけ取っておけば良いよね。
ということで、3~5年生の3学年分の教科書だけを残して、残りは処分することにしました。
片づけは目的意識が大切!
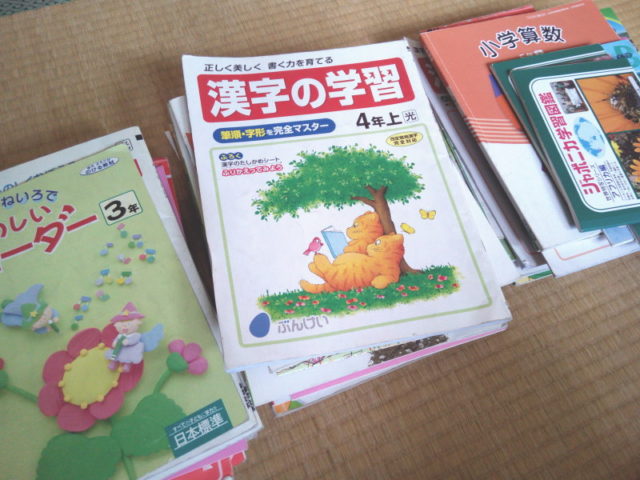
実はこうなってしまっていることは私も気付いていました。ただ、頭を打たないと気付けないと言うか、いくら口で言っても伝わらないものなんですよねー。本人なりにちゃんとできていると思い込んでいるとなおさらです。
片づけでは目的が大切です。何のために片づけるのか、何のためにモノを取っておくのか。そこをよく理解していないと、”なんとなく”片づけたりモノを取っておくことになります。
しかし、なんとなくではダメなのです。今回の場合、息子のために3~5年生の教科書だけを保管しておくことに決めたら、収納スペースはたった1/5程度で済みました。教科書を取っておく目的を「息子が紛失したときのため」と決めるだけで、たったの1/5の量になるのです。
たったそれだけのことで、モノの量が減り、他のモノも片づけやすくなります。また、息子が教科書をなくしても代わりを探すのに掛かる時間や手間も1/5程度で済むことでしょう。
目的をシンプルにするだけで、身の周りもシンプルになっていくのですね。
他のご家庭の教科書の処分の実態
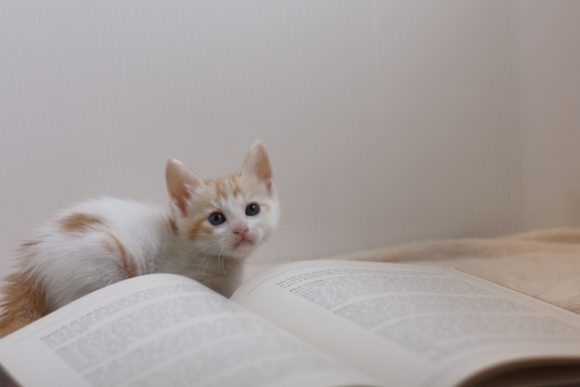
我が家の話だけでは説得力に欠けるところがあると思います。よそのお宅の場合はどうでしょうか。
私が今までにお伺いしたお宅では、お子さんが中高生になってもそれまでの教科書類が全て保管されていたというケースが少なくありませんでした。より顕著なケースでは、お子さんが独立して家を出たにもかかわらずそのままだったり、学校で配布されるプリントもすべて保管されているケースもありました。
そうなると、ダンボール1~2箱というレベルではありません。子供部屋に収まり切らず、廊下までダンボールの山になってしまいます。こういった場合は必要かどうかというよりは、思い出の品として保管していることが多いようです。
アンケートを取ってみました
そこまでの状態になるというのは稀なケースとして、では一体どのタイミングで処分するのが適切と言えるでしょうか。もちろん正解というものはありません。読者の皆さんにアンケートを取っておりますので、参考にしていただきたいと思います。
なお、兄弟姉妹がいる場合は、下のお子さんのために取っておくというケースもあると思いますので、末子の場合を念頭にお答えいただいております。
- 現在or過去を問わず、小学生を対象としています
- ご回答いただくと、すぐに結果が反映されます
- おひとり様1回限りの回答とさせていただきます
- 調査期間:2018/03/20~終了時期未定
アンケート開始から8年が経ちましたが、「旧学年の教材は1~2年分保管しておく」お宅が4割強で最多を占めています。一方で、新学期が始まってから春まで、および夏までに処分というお宅も、合わせて約4割に上るというのも興味深いところです(2023年3月26日現在)。
ちなみに、我が家の場合はだいたい「新学年が始まってから夏までに処分」でした。だいたい新学期が始まってしばらくしてからという感じですね。本当は春休みに処分したほうが気持ちを切り替えやすいんでしょうけど、新学年になってから旧学年の教科書が必要だと言われる可能性があるのでそうしているという感じです。
また、私自身の経験で言うと、中高生になってからは3年生になってから1年生の教科書が必要になることがあったので、基本的には教科書はすべて保管していたと記憶しています。もっとも、処分してしまっても大きな問題ではなかったと思いますが。
以上、我が家の子供たちの教科書の「捨て基準」と、よそのお宅ではどうされているかについてのアンケートを紹介しました。
正解はありません。しかし、参考になる部分はあったと思います。片づけは「決める」ことが大切なので、ご家族とよく相談して決断するようにしましょう。
関連記事




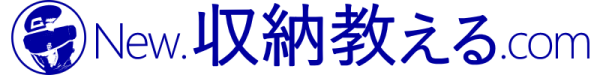
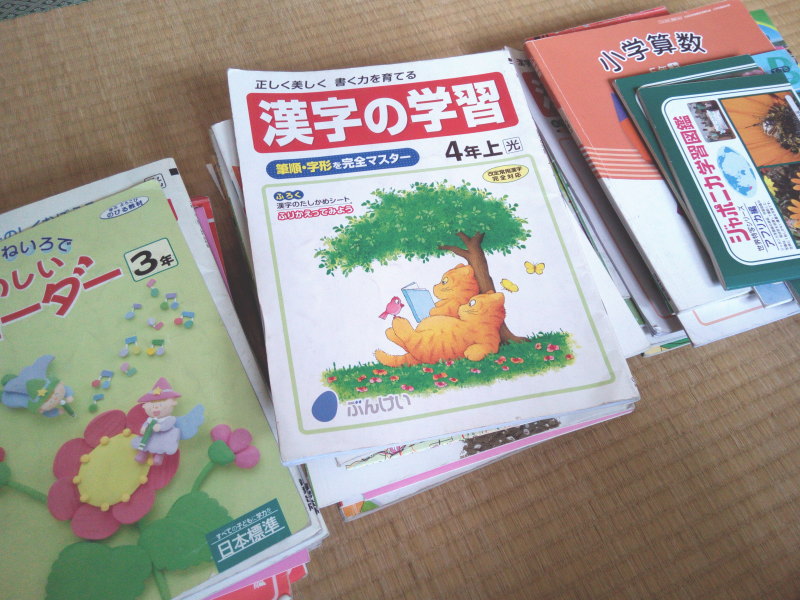


コメント