平安伸銅工業の「LABRICO(ラブリコ)」の発売以来、2×4材などを使って棚を作るDIYパーツが一気に普及したように思います。たまたまDIY女子ブームに乗っかったというラッキーな部分もあったとは思いますけど、むしろDIY初心者でも使い方がイメージしやすく、オシャレなカラーリングを採用したことが大きかったのではないでしょうか。
それはさておき、ラブリコのDIYパーツはラインナップが豊富にあるのですが、その中でも私がイチオシなのは「丸棒シリーズ」です。

ゴツい2×4材よりもやさしい感じがしますし、何より必要な長さでナチュラルな突っ張り棒が作れるというシンプルな使い方ができるのが良いです。必要もないのに買いたくなってしまう衝動を抑えるのが大変で困ってしまいます(苦笑)
それにしても、ラブリコの発売以来ちらほらと類似品が出てきたように、丸棒シリーズもやっぱり狙われてるんですかね。ネットで情報収集をしていたら見つけてしまいました。
アイワ金属・KINOBO
ラブリコの丸棒シリーズによく似ているのは、アイワ金属の「KINOBO」という商品です。アイワ金属はラブリコのシェルフフレームに似た商品を先に発売しているくらいですから、パクったというよりは偶然似た商品をたまたま出遅れて発売してしまったと言ったほうが正しいのかもしれません。

KINOBOは直径24mmの丸棒を使用
ラブリコ丸棒シリーズとの最大の違いは、ラブリコが直径30mmの木製丸棒を使うのに対し、KINOBOは直径24mmのものを使用するということ。
普通なら太い丸棒を使ったほうがシッカリするはずですが、KINOBOのほうが耐荷重が大きいそうです。ラブリコが横向きに突っ張るときに5kgまで、縦向きに8kgまでのところ、KINOBOは横向きで最大12kg、縦向きで10kgとなっています。
もっとも、このあたりはメーカーそれぞれに基準があるので、単純比較はできません。
トレイ
また、ラブリコにはないパーツも用意されています。「トレイ」(ブラック:AP-3023B、ホワイト:AP-3023W)は平安伸銅工業の「DRAW A LINE(ドローアライン)Table A」のお株を奪うようなパーツ。直径はドローアラインの半分程度と小さいですが、手軽にチョイ置き棚を作ることができます。
Cフック
KINOBOを横に渡したときに使える「Cフック」(ホワイト:AP-3018W、ブラック:AP-3018B)というのも何だかドローアラインっぽいパーツですね。S字フックよりもシッカリ安定して掛けることができるので良いと思います。
ラインナップをラブリコと比較
| KINOBO | LABRICO | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 税込価格 | 商品名 | 税込価格 |
| テンションロッド | 743円 | アジャスター | 1,298円 |
| テンションロッド・ロング | 895円 | – | – |
| Cフック2個入 | 356円 | – | – |
| Tジョイント | 330円 | 連結パーツT型2個入 | 748円 |
| Rフック4個入 | 240円 | フック | 638円 |
| シェルフブラケット2個入 | 359円 | 棚受4個入 | 1,188円 |
| トレイ | 570円 | – | – |
| – | – | ジョイント | 748円 |
| – | – | 高さ調整キャップ4個入 | 748円 |
| – | – | 丸キャップ | 418円 |
※すべて2020/10/27現在、KINOBOはホームセンターヤマキシ楽天市場店、LABRICOは平安伸銅オンラインショップ楽天市場店の税込価格
KINOBOは7アイテム×2色で計14アイテム、ラブリコもまったく同じです。ただし、KINOBOはテンションロッド・ロングにラブリコのジョイントのようなパーツが、同じくTジョイントに丸キャップのようなパーツがセットになっているなど、構成が少し異なります。
また、価格はラブリコのほうが高い感じがしますが、これは平安伸銅公式オンラインショップでの価格を参照しているためで、楽天市場の他の店で見るとそんなに変わらないのではないかと思います。
なお、KINOBOのテンションロッドを丸棒に取り付ける際はラブリコのアジャスターと違ってネジで固定する必要があります。その点だけで言うとラブリコのほうが設置に手間がありません。
また、パーツの構成を見てもラブリコのほうが組み立ての自由度が高いように思います。KINOBOは組み替えて2本の丸棒を繋げたいと思ってもテンションロッド・ロングを買うよりほかありませんが、ラブリコならジョイントだけ買うこともできます。T型のジョイントパーツもラブリコならH型に組むことができますが、KINOBOはT型が前提でH型にした場合は滑り止めパーツが余ってしまいます。
そのように考えると、ラブリコのほうが使い勝手が良いように思いますが、KINOBOのほうが線が細い、独自のパーツがあるなどのメリットもあります。結局はニーズ次第で選ぶという感じですかね。
関連記事




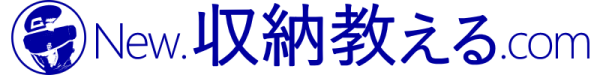









コメント