テレビボードや食器棚、チェストなどの収納家具を選ぶ際、どんなポイントをチェックしますか?
まず予算、サイズ、扉や引出しなどの構成、材質、色合いやデザインなどを見ることが多いと思います。日本製か海外製かといった点を気にする人もいるかもしれません。
家具のプロが品定めをする際はそういった外から見えるところも重要ですが、むしろ見えない部分をシッカリとチェックします。引出内部材はどんなものが使われているか、引出しのスライドレールや扉のヒンジ金具はどこのメーカーか、棚ダボは挿し込み式かネジ込み式かなどです。また、棚板は厚みだけでなくベタ芯かフラッシュ(中空合板)かなども確認します。
オープンラックを除いてほとんどすべての収納家具には背板が備わっています。背板は棚の奥にモノが落ちないようにするためだけでなく、外箱が左右に歪まないようにするための重要なパーツです。ここもただハメ込まれているだけなのかタッカーで打ち付けられているのかなどをチェックするのですが、化粧されているかどうかも重要なポイントです。
※この記事は2024年6月17日時点の情報に基づいています
背面化粧仕上げとは

上写真はいずれもカラーボックスの背面です。
左側は天板と側板のパーティクルボードや背板のMDF合板が剥き出しの状態。昔は杉板、ラワンやシナの合板が使われることも多かったと思います。
右側は天板と側板の木口(こぐち)に化粧テープが貼られ、背板はプリント紙貼りとなっています。この右側の状態を背面化粧仕上げと言います。
背面化粧仕上げのメリット&デメリット
メリット
- 見た目が美しい
- ホコリがつきにくい
- 湿気やカビの影響を受けにくい
背面化粧仕上げの収納家具にはどのようなメリットがあるのでしょうか。まず、見た目が美しいことが挙げられます。壁に寄せているときは見えないですが、部屋の真ん中に置いても問題なく、布などで覆い隠す必要がありません。
実用性の面ではホコリがつきにくいことがメリットです。化粧されていないパーティクルボードやMDFは表面がザラザラしているのでホコリがつきやすいです。おまけに、雑巾で拭こうとすると、パイルが引っ掛かってしまいます。ホコリもなかなか取れません。
さらに、パーティクルボードやMDFはダイレクトに湿気を吸いやすく、ホコリと相まってカビも発生しやすいです。しかも、一度カビが発生するとなかなか取れません。プリント紙で化粧されていれば絶対にカビが発生しないわけではないものの、化粧されていないよりはその可能性は低いと言えます。
デメリット
- コストが上がる
一方で、背面を化粧仕上げにするには相応のコストが掛かります。木口テープやプリント紙のコストだけでなく、それを貼る手間も必要です。いずれもわずかなコストと言えますが、見えないところや消費者が重視しないところのコストを削るのはどの業界でも同じでしょう。
一昔前は背面が化粧された家具は高級家具に限られていました。しかしながら、近年はカラーボックスなどの安価な家具にも採用されることが増えています。
また、国産家具でも以前はシナや桐で化粧されていたのが、近年になってプリント紙に切り替える動きもあります。天然木突板のほうがコストが掛かるので、コストを削るためではありません。ただ、節などが入った二級品を使うため「キズがある」とクレームが入ることがあり、そんな風に言われるならプリント紙にしたほうがマシとメーカーが判断せざるを得ないためです。
ともあれ、背面が化粧かどうかで変わるコストは僅かです。それなら背面が化粧された家具を選んだほうが良いですよね。店頭ならすき間から覗いてみたり、ネットで購入する場合はちゃんと写真が掲載されているものを選ぶようにしましょう。
関連記事




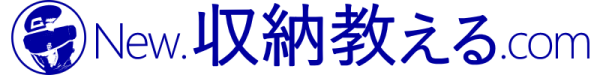



コメント